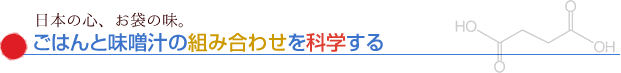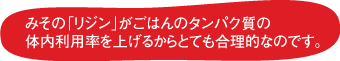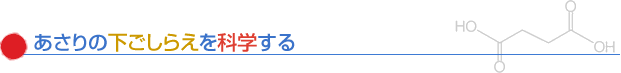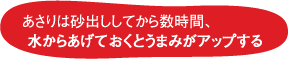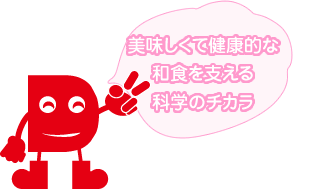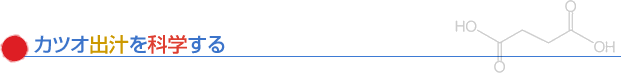
 日本料理のダシの素材は、鰹節、昆布、煮干、乾し椎茸など。主に乾物である事がいえます。はじめは保存目的であった"乾す""干す"という作業が、実は素材のうま味を増やし、うま味を出しやすくしていたのです。
日本料理のダシの素材は、鰹節、昆布、煮干、乾し椎茸など。主に乾物である事がいえます。はじめは保存目的であった"乾す""干す"という作業が、実は素材のうま味を増やし、うま味を出しやすくしていたのです。カツオ出汁の材料であるカツオ節の製造工程は大まかに言うと、
①切る②煮る③燻す④発酵させる──の4段階。
発酵は仕上げの工程。カビを生やしては天日干ししてはらい落とし、またカビを生やして......を数ヶ月かけて繰り返すと、カビは、生き残るためにカツオの水分を吸収し、節が乾燥していきます。 そうして、カビの働きにより、生のカツオに含まれるアデノシン3リン酸といsう核酸が分解されイノシン酸といううま味成分に変化し、カツオ自身の酵素や他の微生物によって分解されるのを防ぎ、長期保存できる形に生まれ変わるのです。 これを枯節といい、削った製品には"かつおぶしけずりぶし"と表記されます。
これらの工程には4~6ヶ月を要します。鰹節は世界で一番硬いたべものといわれています。
昆布だしのうまみ成分のグルタミン酸にかつおぶしのうまみ成分イノシン酸を合わせると、うまみが増す「相乗効果」は昔からの日本人の知恵でわかっていました。
うまみ1の昆布と、うまみ1のかつおぶしを合わせると、そのだしのうまみは7倍になります。
つまり合わせだしは、1+1=7というミラクルが起こるのです!
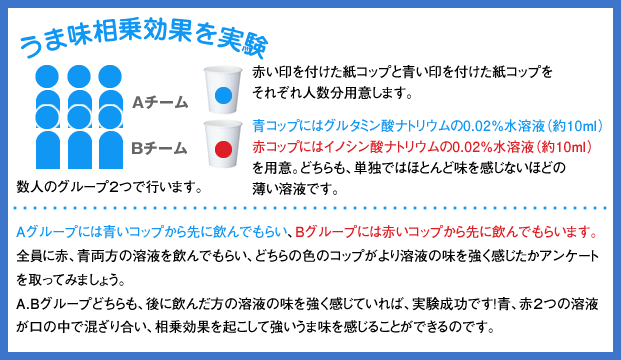
 人の舌の細胞表面には、味を感じる「味覚受容体」と呼ばれるタンパク質があり、これまで、「甘味」、「うまみ」、「苦味」を感じる受容体が見つかっているのですが、グルタミン酸とイノシン酸は、同じうまみ受容体でもそれぞれ別の場所で結合するからだということが解ってきています。
人の舌の細胞表面には、味を感じる「味覚受容体」と呼ばれるタンパク質があり、これまで、「甘味」、「うまみ」、「苦味」を感じる受容体が見つかっているのですが、グルタミン酸とイノシン酸は、同じうまみ受容体でもそれぞれ別の場所で結合するからだということが解ってきています。和食が、素材の味と色を生かし、塩分、油分、糖分を抑えることができるのは、出汁の科学の賜物ですね。
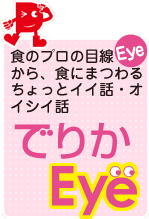

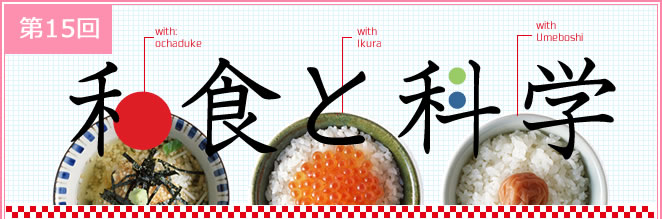
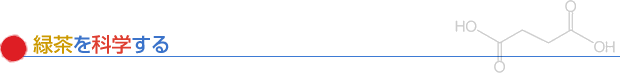
 緑茶は水の温度と浸出時間で溶け出る成分量が変わる。
緑茶は水の温度と浸出時間で溶け出る成分量が変わる。